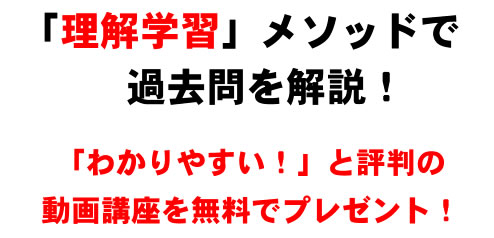AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
- AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
- 甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
- AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
- Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 (AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。)AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
【答え】誤り
【解説】
建物賃貸借契約において、一定要件の下で契約の更新がない旨を定めると定期建物賃貸借契約となります。一定要件とは下記内容です。
- 公正証書による等の書面によって契約
- あらかじめ、建物賃借人に対し、「契約の更新がなく、期間の満了により建物賃貸借は終了する」旨を書面を交付して説明
本肢は、単に書面で契約すれば足りるとなっているので、(1)の要件だけ満たせば、更新ナシの契約にできることになります。 これは誤りです。(1)だけでなく(2)も満たさないと更新ナシの契約にはできません。
選択肢2 (AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。)甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
【答え】誤り
【解説】
居住用建物の賃貸借においても、定期建物賃貸借にすることは可能です。よって、甲建物が居住の用に供する建物である場合でも、「契約の更新がない旨」の特約を定めることはできます。 よって、誤りです。
選択肢3 (AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。)AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
【答え】誤り
【解説】
建物賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新される)。ただし、法定更新後の契約期間は、従前の契約を引き継がず、「期間の定めがないもの」となります。よって、 本肢は「3月前」という記述がが誤りです。 正しくは「1年前から6か月前まで」です。この内容は理解すべき内容なので、個別指導では、理解学習勉強法を使って解説します!
選択肢4 (AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした。)Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
【答え】正しい
【解説】
問12-4:賃貸借契約が解約の申入れによって終了する場合、転貸借に通知をすることで対抗できます。.jpg)
賃貸人Aは、賃借人Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、原則、転借人Cに「AB間の賃貸借契約が終了する旨」の通知をしなければ、賃貸借契約の終了を転借人Cに対抗することができません。 よって、本肢は正しいです。上記を言い換えると、上記通知をしなければ、転借人Cは「BC間の転貸借契約」のとおり、住み続けることができます。

まとめ 定期建物賃貸借契約は要件が重要です!要件はすべて頭に入れた上で問題を解けるようにしましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
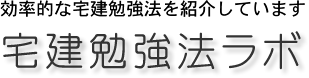
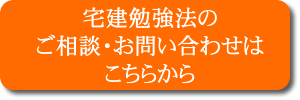
問12-4:賃貸借契約が解約の申入れによって終了する場合、転貸借に通知をすることで対抗できます。.jpg)