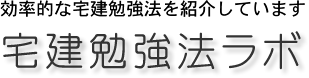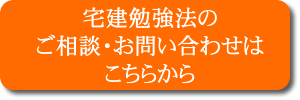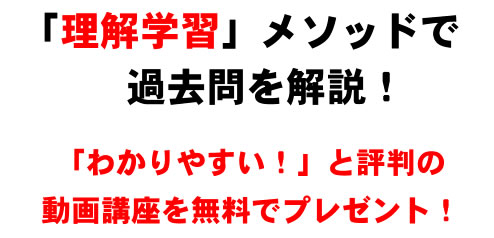宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
- A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金 を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
- A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
2
解答と解説
【解答】2
選択肢1 A社は、甲県の区域内に新たに支店を設置し宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業の免許を受けた後すぐに、事業開始はできません。営業保証金制度を利用する場合、宅建業の免許を受けて、営業保証金を供託して、供託した旨の届け出をした後にやっと事業を開始することができます。つまり、「供託した旨の届出」→「事業開始」という流れです。
選択肢2 甲県知事は、A社が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社が届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
【答え】正しい
【解説】
免許権者は、宅建業の免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。この場合の免許取消処分は任意なので、免許取消処分をしなくてもよいです。
選択肢3 A社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金 を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者(以下この問において「還付請求権者」という。)に対して公告しなければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対して公告する必要はない。
【答え】誤り
【解説】
宅地建物取引業者は、廃業、支店の廃止により営業保証金を取り戻す場合、6か月以上の期間を定めて公告をしなければなりません。これは、当該宅建業者と取引をして損害を受けた取引相手がいた場合に、勝手に営業保証金を取り戻されて、供託所に還付請求できなくなってはかわいそうなので、公告などをして、「営業保証金を取り戻しますよ!」とお知らせをするものです。お知らせは官報に掲載して行われるのですが、今はインターネット版官報があるので、そこで見る場合がほとんどです。
選択肢4 A社は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、廃業の日から10年経過していれば、還付請求権者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
【答え】誤り
【解説】

宅地建物取引業者であった者が、営業保証金を取り戻すことができるのは、取引が結了した時(例えば、引渡日)から10年を経過したときです。廃業の日から10年経過していても、まだ、取引結了時から10年を経過していない場合もあります。そのため、誤りです。

まとめ 本問はすべてひっかけ問題といえます。選択肢2は正しい記述ではあるものの、数字を変えるだけでひっかけ問題になります。ひっかけ問題に引っかからないためにも、きちんと問題文は読むようにしましょう!ひっかけ問題対策のノウハウは
個別指導で解説します!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事