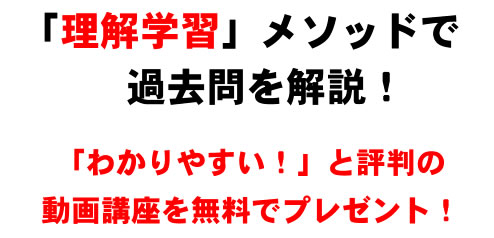宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第 1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
- Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
- Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
3
解答と解説
【解答】3
選択肢1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
【答え】違反しない
【解説】
問33-1:宅建業者間の取引なので、8種制限の適用がない図.jpg)
宅建業者間の取引の場合、宅建業法の8種制限は適用されません。 したがって、売主業者Aは、手付金等の保全措置も講じる必要はありません。また、手付金額の制限も適用されないので、手付金の額についても制限はありません。したがって、売主業者Aは、手付金について、代金の2割(1000万円)を超えて受領することもできます。(もちろん手付金1000万円受領しても問題ありません) つまり、本肢は正しい記述です。
選択肢2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
【答え】違反しない
【解説】
問33-2:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合なので、手付金額の制限が適用される.jpg)
売主が宅建業者、買主が非宅建業者なので、8種制限の一つである手付金等の保全措置のルールは適用されます。 したがって、未完成物件(建築工事完了前の建物)の場合、代金の5%または1000万円を超えて手付金等を受領する場合、保全措置が必要です。 そして、代金の5%は、250万円です。 本肢は、手付金1000万円を受領する場合なので、手付金等の保全措置が必要です。この点は、保全措置を講じているので違反ではありません。しかし、一方で、手付金額の制限のルールも適用されます。 手付金額の制限では、代金5000万円の2割(=1000万円)を超える手付金は受領できません。 本肢は1000万円ピッタリの手付金を受領しているので、これも違反はしていません。よって、本肢は、違反ではありません。
選択肢3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
【答え】違反する
【解説】
問33-3:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合なので、手付金等の保全措置が適用される図.jpg)
売主が宅建業者、買主が非宅建業者なので、8種制限の一つである手付金等の保全措置のルールは適用されます。 手付金100万円については代金の5%(250万円)を超えていないので保全措置は不要です。 次に中間金を受領する場合、手付金100+中間金500=合計600万円を受領することになります。未完成物件の場合、代金の5%(250万円)を超えて手付金や中間金を受領する場合、受領前に600万円分を保全しなければいけません。 したがって、本肢の場合、中間金を受領する前に、600万円を保全しないと違反となるので、本肢は宅建業法違反です。
選択肢4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
【答え】違反しない
【解説】
問33-4:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合で、手付金等の保全措置をせず、所有権を移転したtokiの図.jpg)
売主が宅建業者、買主が非宅建業者なので、8種制限の一つである手付金等の保全措置のルールは適用されます。選択肢3のように原則、中間金を受領する前に600万円分の保全措置が必要です。 しかし、買主Eへの所有権移転登記がされたときは、例外として保全措置は不要です。よって、本肢は宅建業法違反ではありません。 この例外規定は理解をすれば、頭に入れやすい部分なので、理解学習を実践するとよいでしょう!理解すべき部分は、個別指導で解説します。無料講座でも、このような理解学習の一部を解説しているので、ぜひご利用ください。

まとめ 8種制限は、ルールを理解すれば、解けます。ひっかけ問題などにひっかかって間違う方は、理解学習ができていない証拠です。丸暗記学習では、このような得点すべき問題を失点してしまうので、どれだけ勉強しても合格するのが難しくなります。理解学習ができていないことを知ったらすぐに理解学習に勉強の仕方を変えていきましょう!これも、宅建合格するためです!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
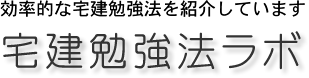
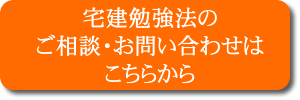
問33-1:宅建業者間の取引なので、8種制限の適用がない図.jpg)
問33-2:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合なので、手付金額の制限が適用される.jpg)
問33-3:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合なので、手付金等の保全措置が適用される図.jpg)
問33-4:売主が宅建業者で、買主が宅建業者でない場合で、手付金等の保全措置をせず、所有権を移転したtokiの図.jpg)