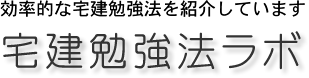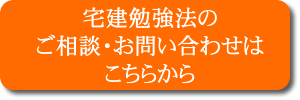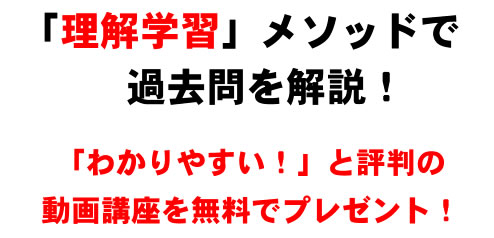次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
1
解答と解説
【解答】1
選択肢1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
【答え】正しい
【解説】
案内所には、契約締結等を行うか否かに関係なく標識が必要です。そして、契約締結等をしない案内所(専任の宅建士をしなくてよい案内所)の標識には「クーリングオフの適用がある旨」を記載しなければなりません。よって、本肢は正しいです。この内容はイメージできれば簡単に解けます!そのため、個別指導では、イメージの仕方まで解説しています!無料講座でも、イメージの仕方の一部について解説しているので、ぜひご利用ください。
選択肢2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
【答え】誤り
【解説】
契約を締結しない旨の意思や勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています。 勧誘した従業員とは別の従業員であっても、同じ宅建業者であれば、情報共有して、お客様に迷惑をかけないようにするのが当然です。 一度、勧誘を断っているのに、再度勧誘されては、お客様は迷惑です。そういった迷惑行為は宅建業法で禁止されます。
選択肢3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(宅建業法第44条)に該当する。
【答え】誤り
【解説】 不当な履行遅延の禁止の対象とされているのは、下記3つです。
- 宅地・建物の登記
- 宅地・建物の引渡し
- 取引に係る対価(売買代金等)の支払い
本肢のような「媒介契約に基づく報酬(仲介手数料)の支払い」は含まれていません。 つまり、報酬の支払いを拒むこと(遅らせること)は、不当な履行遅延(宅建業法第44条)には該当しません。よって、誤りです。
選択肢4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。この点は正しいです。誤っているのは、そのあとの文章です。従業者名簿には、「従業者でなくなった日」も記載しなければいけません。つまり、退職した従業者に関する事項も、従業者名簿への記載の対象です。
<従業者名簿の記載事項>
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅地建物取引士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- 当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日

まとめ 本問はすべて基本事項です。業務上の規制に関する問題ですが、これらは、条文を確認しておけば解ける問題ばかりです。しっかり宅建業法の条文を確認しておきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事