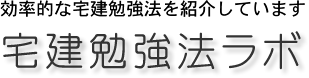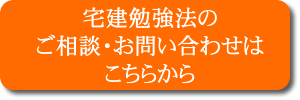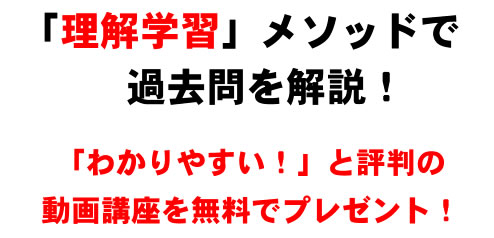AがBから事業のために、1,000万円を借り入れている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。
- AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
- Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
- Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在をしらなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。
【答え】誤り
【解説】
通常、債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、混同により消滅します。しかし、債権者と債務者が婚姻しても、債権は消滅しません。言い換えると、婚姻によって、混同の効果は生じないということです。
混同の解説はこちら>
選択肢2 AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
【答え】誤り
【解説】
養子縁組により養子になっても、当然に養親の借入金債務について連帯責任を負うことはありません。よって、本肢は誤りです。正しい文章に変えると「AがCと養子縁組をしたとしても、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負わない」という文章になります。
選択肢3 Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
【答え】誤り
【解説】
本問は、Aの唯一の資産である不動産を相続人Dが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合の話です。この場合、被相続人Aの債務(相続債務)は誰が相続するかが問題です。この点について法律では「法定相続分で債務は分ける」こととなっています。つまり、Eは、プラスの財産を相続していなくても、債務のみ相続します。
選択肢4 Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在をしらなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。
【答え】正しい
【解説】
相続人は、単純承認をしたときは、被相続人の全ての権利義務を承継します。 したがって、相続人FがAの借入金債務の存在を知らなかったとしても、当該借入金債務を相続します。

まとめ 養子縁組については、あまり出題されないですが、基本的な内容なので、勉強しておきましょう。また、混同については、連帯債務や連帯保証の分野でも出題されるので理解が必要です。「相続債務が法定相続分で分けられること」、「単純承認すると、債権債務のすべてを相続すること」は基本事項なので頭に入れておきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事