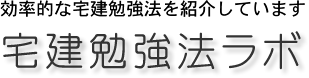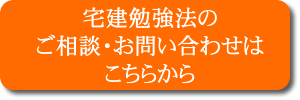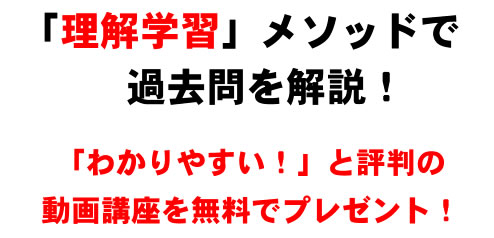①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
- ①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
- ①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
- ①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
1
解答と解説
【解答】1
選択肢1 ①不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
【答え】誤り
【解説】
①不動産質権
不動産質権者は、原則、利息を請求することができません。
<理由>不動産質権の質権者は、動産質権者と異なり、不動産の使用・収益が認められています。そのため、この使用・収益できる利益が、利息と同価値と考えて、利息請求ができないことになています。よって、①の記述は誤りです。
②抵当権
抵当権は、原則、利息・遅延損害金に関し、満期となった最後の2年分についてのみ抵当権の行使が可能です。この点は正しいです。「満期となった最後の2年分」については、個別指導で解説します!
選択肢2 ①不動産質権は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②抵当権は、存続期間に関する制限はない。
【答え】正しい
【解説】
①不動産質権
不動産質権の存続期間は、最長で10年です。10年を超える不動産質権を設定した場合、10年に短縮されます。よって、正しいです。
②抵当権
抵当権の存続期間に、制限はありません。何年で設定しても有効です。よって、正しいです。
選択肢3 ①不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
【答え】正しい
【解説】
①不動産質権
不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件となっています。
②抵当権
抵当権は、設定契約の締結が効力の発生要件です。
よって、本肢は正しいです。
選択肢4 ①不動産質権も②抵当権も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
【答え】正しい
【解説】
①不動産質権も②抵当権も物権です。不動産に関する物権は、登記が対抗要件です。よって、本肢は正しいです。選択肢3の効力発生要件と本肢の対抗力の発生要件は異なるので注意をしましょう!違いは個別指導で解説します!

まとめ 本問は、不動産質権と抵当権の違いについても問題ですが、内容的にはすべて基本問題なので、理解をした上で頭に入れておきましょう!丸暗記だと、本試験で頭が真っ白になるので注意しましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事