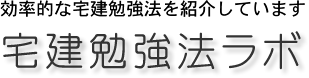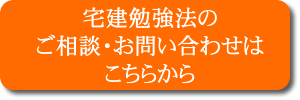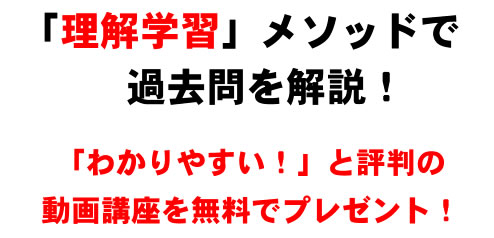宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。
- 建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
- 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから110,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。
- 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。
- C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 建物を住居として賃借する場合(借賃10万円)、媒介業者C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。
【答え】正しい
【解説】
居住用建物の賃貸借の場合、媒介業者が依頼者の一方から受領できる報酬額の限度は、原則、賃料の1/2+消費税です。ただし、例外として、依頼者から承諾を得ている場合、最大で賃料の1か月分+消費税までもらえます。よって、本肢の場合、「賃料の1/2+消費税」は、55,000円なので、C社が受領できる報酬額の上限は原則、55,000円です。したがって「媒介業者C社は、Dから承諾を得ているときを除き、55,000円を超える報酬をDから受領することはできない」という記述は正しいです。この問題文の意味が理解できない方は、個別指導で解説します!宅建試験に合格するための勉強法として一番重要なことは問題文の理解です!本肢の「~を除く」という文言は本試験でもよく出題されるし、読んだときにすぐに問題文を理解できないと、制限時間内に問題を解けず、焦ってしまいます。早い段階で理解しておきましょう!
選択肢2 建物を店舗として貸借する場合(借賃10万円)、代理業者A社がBから110,000円の報酬を受領するときは、媒介業者C社はDから報酬を受領することはできない。
【答え】正しい
【解説】
賃貸借における代理業者が、依頼者から受けることのできる報酬の額は、当該宅地又は建物の「賃料の1か月分+消費税」が上限です。そのため、代理業者A社がBから受領できる報酬額は、最大で、110,000円です。そして、賃貸借契約に関係する宅建業者(代理業者A社と媒介業者C社)が受領する報酬額の合計の上限も「賃料の1か月分+消費税」なので、110,000円です。したがって、「代理業者A社がBから110,000円の報酬を受領するときは、媒介業者C社はDから報酬を1円も受領することはできない」ので、本肢は正しいです。報酬額の計算については、ルールを覚えれば簡単に解けます。得点源になるので、掛け算ができる人は、解けるようにしましょう!個別指導では詳しく解説します!
選択肢3 建物を店舗として貸借する場合(借賃10万円)、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、代理業者A社及び媒介業者C社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。
【答え】正しい
【解説】
居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受があるものについては、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、「売買と同様の計算した額」と「賃料の半月分+消費税(承諾を得ている場合は1か月分+消費税)」の大きい方が報酬額の上限となります。
■売買と同様の計算方法の場合
(300万円×4%+2万円)×2×1.1=308,000円
■賃料の半月分+消費税(承諾を得ている場合は1か月分+消費税)の計算でいくと
最大、110,000円
つまり、大きい方である308,000円が報酬額の上限となります。よって、「代理業者A社及び媒介業者C社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内」なので正しいです。
この点については詳細解説が必要なので詳細解説は個別指導で解説します!
選択肢4 媒介業者C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。
【答え】誤り
【解説】
宅地建物取引業者が受領できるお金は、「国土交通大臣が定める報酬額」と「依頼者の依頼によって行う広告の料金等」に限られます。契約書作成費用を別途受領することはできません。

まとめ 宅建業法上の報酬計算問題は、ルールが分かって、掛け算ができれば、必ず解答できるので、掛け算ができる人は、解けるようにしておいた方が良いです。ここで1点を落とすのはもったいないです。ただ、計算が苦手な方は、計算の勉強をすることから始めるのは非効率なので飛ばしていただいてもよいでしょう。
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事