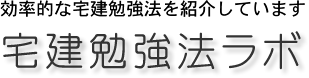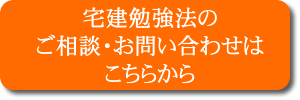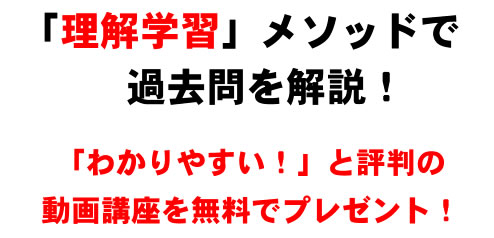物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
1
解答と解説
【解答】1
選択肢1 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
【答え】誤り
【解説】

「一般債権者の差し押さえ」と「抵当権者の物上代位権に基づく差押え」が競合した場合、「一般債権者の申し立てによる差押命令の第三債務者(建物賃借人)への送達」と「抵当権設定登記」の先後によって決まります。 本肢は、①Aの抵当権設定→②一般債権者が建物賃料債権の差押え、という時系列なので、抵当権者Aが優先します。よって、抵当権者Aは、当該賃料債権に物上代位することができます。 本肢は「Aは当該賃料債権に物上代位することができない」という部分が誤りです。
選択肢2 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
【答え】正しい
【解説】

抵当権を実行している(競売の手続きに入っている)ということは、被担保債権について債務不履行があったことを意味します。被担保債権について債務不履行があった場合、法定果実(本肢では建物賃料)にも抵当権の効力が及びます。したがって、抵当権者Aは、抵当権を実行をしていても、抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができます。よって、本肢は正しいです。
選択肢3 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
【答え】正しい
【解説】

抵当権不動産が火災により焼失して、損害保険金が下りる場合、抵当不動産が損害保険金請求権に価値が変換したと考えられます。そのため、損害保険金請求権にも抵当権の効力は及びます。ただし、損害保険金が支払われる前に抵当権に基づく差押えが必要です。よって、本肢は正しいです。
選択肢4 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
【答え】正しい
【解説】

問題文の状況は、抵当建物(抵当権が付いた建物)が賃貸、さらに転貸された場合、賃借人Cは、「転貸賃料債権」を有します。そして、判例によると、抵当権者Aは、抵当権に基づいて、転貸賃料債権を物上代位することはできない、としています。これは理由をしっかり理解する必要があります。そのため、理由については個別指導で解説します!無料講座でも、このような理解すべき部分の一部を解説しているので、ぜひ、ご参加ください。宅建合格するための効率的な勉強法もお伝えしています。

まとめ 本問は、抵当権に基づく物上代位に関する問題ですが、非常に重要な問題であり、理解すべき問題です。合否の分かれ目になる問題なので、すべて理解しておきましょう!理解すべき部分および理解学習については、
個別指導で解説します!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事