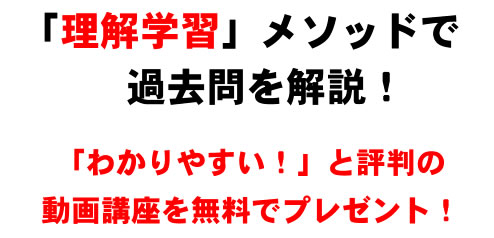宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
- Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
- Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 宅建業者Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者間で適用されないルールは、8種制限だけです。37条書面の作成交付に関するルールは8種制限ではないので、宅建業者間でも適用されます。 したがって、宅地の売買における引き渡し時期については37条書面の必要的記載事項なので、必ず37条書面に記載しなければなりません。よって、本肢は誤りです。37条書面の記載事項と35条書面の記載事項で混乱する方は、整理の仕方を頭に入れると、本試験でも解けるようになります!この整理の仕方は、個別指導で解説します!
選択肢2 宅建業者Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。
【答え】誤り
【解説】
売買における代金の額は、37条書面の必要的記載事項です。ここでいう代金には、消費税相当額も記載する義務があります。したがって、本肢は誤りです。
選択肢3 宅建業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。
【答え】誤り
【解説】
問42-3:宅建業者間の取引について、宅建業者Dが媒介する場合の図.jpg)
宅建業者間の取引であっても、37条書面の作成・交付のルールは適用されます。本問の場合、37条書面には、取引に関係する宅建業者の宅建士が記名する必要があります。つまり、買主Eに交付する37条書面には、AとDの双方の宅建士が記名しなければなりません。したがって、本肢は誤りです。
選択肢4 宅建業者Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。
【答え】正しい
【解説】
問42-4:宅建業者が貸借の代理を行う図.jpg)
売買又は貸借の代理を行う宅建業者は、貸主と借主双方に対して37条書面を交付しなければなりません。 本肢の場合、代理業者Aは、FとGの双方に対して37条書面を交付しなければならないので、本肢は正しいです。これは売買の場合も同じなので、併せて頭に入れておきましょう!37条書面の交付相手、35条書面の交付相手は、理解しないとひっかけ問題に引っかかるので、理解の仕方は個別指導で解説します!

まとめ この問題を丸暗記している方は、本試験でひっかけ問題が出題されたときに失点してしまいます。これが合否の分かれ目になります。 勉強した分だけ実力を上げるためにも、しっかり理解をしていきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
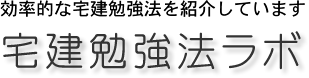
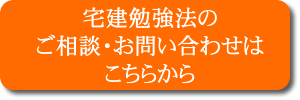
問42-3:宅建業者間の取引について、宅建業者Dが媒介する場合の図.jpg)
問42-4:宅建業者が貸借の代理を行う図.jpg)