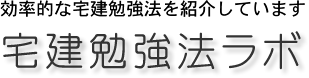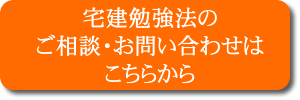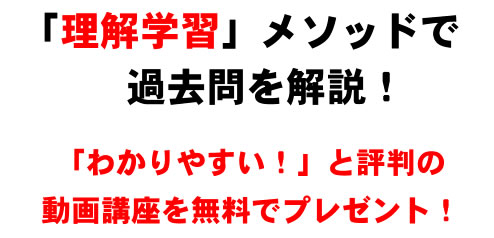2023-12-11
宅建過去問 令和元年(2019年) 問36 問題解答と解説付き
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
- Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
- 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
- Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
▼ 解答と解説はこちら