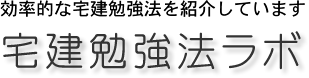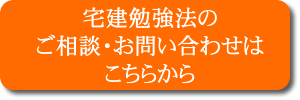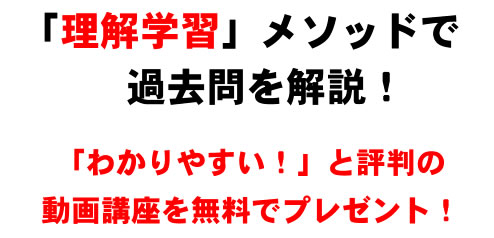建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
- 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
【答え】誤り
【解説】
居室を有する建築物は、その居室内においてホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないように、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければなりません。 つまり、ホルムアルデヒドの使用がすべて禁止されているわけではありません。 よって、誤りです。 本肢は、対比勉強法を使って暗記すると効率的です!そのため、個別指導では対比ポイントも含めて解説します!
選択肢2 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
【答え】誤り
【解説】
敷地内の通路の幅員については、敷地内には、避難経路を確保するため、屋外に設ける避難階段及び建物の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m(階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cm)以上の通路を設けなければなりません。 本肢は「2m」となっているので誤りです。「1.5m」とすれば正しいです。
選択肢3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
【答え】誤り
【解説】
防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。 本肢は、防火構造としているため誤りです。正しくは耐火構造です。
<理解>
「防火構造」は、建物の外部で火災が起きたときに、当該建物が火災に巻き込まれないために必要とされる外壁や軒裏の構造のことです。 一方、「耐火構造」は、建物内部で火災が起きた際にも、当該建物自体の倒壊や周囲への延焼を防ぐような構造のことです。 建物内部で火災が発生しても、周囲の建物に燃え広がらない構造だからこそ、外壁を隣地境界線に接して設けることができるのです。この解説が理解学習勉強法を用いた解説です。法令上の制限は丸暗記勉強ではなく、理解勉強法を使えば、頭に定着します!個別指導では、このような理解学習勉強法を使って解説をしています! だからこそ、勉強したら勉強した分だけ実力を上げることができ、法律知識ゼロの方でも、一発合格していただいています! 次の試験で合格したい方はぜひ、個別指導をご検討ください。
選択肢4 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。
【答え】正しい
【解説】
建築物は、原則、検査済証の交付を受けた後でないと使用することができません。 ただし、例外として、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときには、検査済証の交付を受ける前でも仮に使用することができます。 本肢は、例外にあたるので、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができます。よって、正しいです。

まとめ 本問は選択肢2は知らない人も多いですが、それ以外は解けないといけない問題です。3つの選択肢が正解できれば、この問題は得点できます。つまり、必ず得点すべき問題といえます。
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事