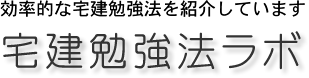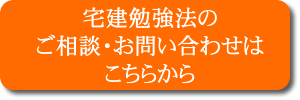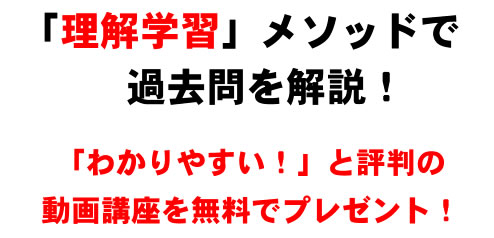宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
- Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 Bが建設業者である場合、宅建業者Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
【答え】誤り
【解説】
住宅瑕疵担保履行法における資力確保措置の必要があるのは、売主が宅建業者であり、買主が宅建業者でない場合です。 そして、本肢は、買主が建設業者(宅建業者ではない)なので、売主である宅建業者Aは、資力確保措置が必要です。よって、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない」は誤りで、正しくは「住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う」です。
選択肢2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません。本肢は「基準日から3週間を経過した日以後」が誤りです。
選択肢3 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
【答え】誤り
【解説】
宅建業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、売買契約を締結するまでに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければなりません。本肢は、「新築住宅を引き渡すまでに」となっている点が誤りです。正しくは「売買契約を締結するまでに」です。
選択肢4 Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
【答え】正しい
【解説】
供託すべき住宅販売瑕疵担保保証金を計算する際の新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、新築住宅の中でも床面積が55㎡以下の住宅は、2戸をもって1戸として計算します。例えば、床面積が55㎡以下の住宅が10戸あれば、5戸として考えます。

まとめ 住宅瑕疵担保履行法は、出題される部分が決まっているので、過去問を中心に勉強すれば得点できる確率も高くなります。範囲を広げず、過去問と模試を中心に勉強していきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事