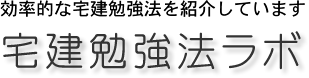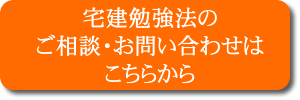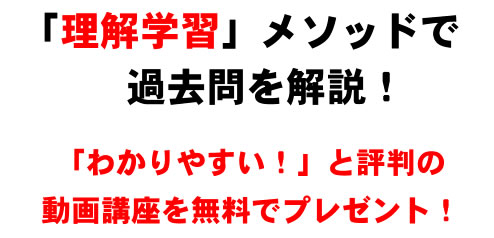宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
- AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
- AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する許面に記名押印する必要はない。
- Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
3
解答と解説
【解答】3
選択肢1 宅建業者AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
【答え】誤り
【解説】
媒介契約書に記載すべき事項は下記の通りです。「標準媒介契約約款に基づくか否かの別」は、媒介契約書(34条書面)の記載事項なので記載しなければなりません。
- 宅地・建物の特定に必要な表示
- 売買価額(交換の場合は評価額)
- 一般媒介・専任媒介の別
- 媒介契約の有効期間・解除に関する事項
- 指定流通機構への登録に関する事項
- 報酬に関する事項
- 既存建物(中古建物)の場合:建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項・
- 契約違反に対する措置
- 標準媒介契約約款に基づくか否かの別
これらはすべて重要な内容なので、それぞれどういうことなのか、内容まで理解をしておきましょう!個別指導では細かい内容も含めて解説いたします!
選択肢2 宅建業者AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
【答え】誤り
【解説】
指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構に通知しなければなりません。契約したら遅滞なく通知するのであって、引渡しが完了するまで待ちません。この問題は理解すべき部分があるのですが、その点については個別指導でお伝えします!
選択肢3 宅建業者AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する許面に記名押印する必要はない。
【答え】正しい
【解説】
媒介契約書に記名押印する義務があるのは宅建業者であって宅建士ではありません。したがって、「宅建士は、34条書面(媒介契約書)に記名押印する必要はない」ので、本肢は正しいです。 宅建士について記名義務があるのは、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約時締結書面)です。この点は併せて覚えておきましょう!
選択肢4 宅建業者Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
【答え】誤り
【解説】
媒介契約書には「売買すべき価額」を記載しなければいけません。これは、一般媒介、専任媒介契約問いません。これは、選択肢1の関連問題です。選択肢1の媒介契約書の記載事項の内容は、一般媒介であっても専任媒介であっても記載すべき内容なので頭に入れておきましょう!

まとめ 媒介契約(34条書面)の内容は、対比して覚えるべき部分が多いです。一般媒介と専任媒介との対比、35条書面や37条書面との対比、色々対比すべき部分があるので、表を使って整理していくとよいでしょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事