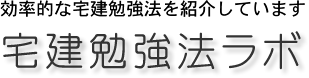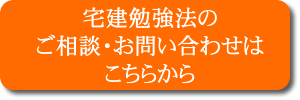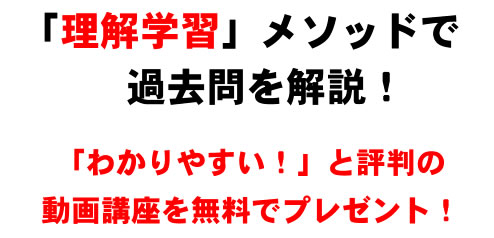Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
- Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
- AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
- AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに転貸した。
BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
【答え】誤り
【解説】

Bが、Aに無断でCに転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができません。よって、「転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる」という記述は誤りです。背信的行為と認められない場合、AはAB間の賃貸借契約を解除できません。
選択肢2 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに転貸した。
Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
【答え】誤り
【解説】
AB間の賃貸借契約が賃借人Bの債務不履行により契約解除となる場合、転借人Cは賃貸人Aに対抗できません。たとえ、BがAの承諾を得て転貸をしていたとしても、Bに賃料不払いがあれば(Bが債務不履行になれば)、AはCに対して甲建物の明け渡しを請求できます。よって、本肢は誤りです。転借人Cは明渡さないといけないです。
選択肢3 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに転貸した。
AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
【答え】誤り
【解説】

AB間の定期建物賃貸借契約は、更新がないため、期間の満了により、当然に終了します。そして、BC間の転貸借契約は、このAB間の賃貸借契約があるから存在する契約なので、AB間の賃貸借契約が終了する以上、当然に、転貸借契約も終了します。この場合、BC間での正当事由は不要です。よって、本肢は誤りです。
ちなみに、建物賃貸人Aは、賃貸借が終了することについて、転借人Cに通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができないです。しかし、このことは、本肢では質問されていないので、考えなくても大丈夫です。
選択肢4 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに転貸した。
AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
【答え】正しい
【解説】

定期建物賃貸借契約においては、賃料の増額請求できない特約および減額請求できない特約は有効となります。賃借人に不利となる減額請求できない特約も有効なので優位しましょう!この点については、理由を理解しておいた方が良いので、個別指導で解説します!理解学習の一部は、無料講座でも勉強できますので、参考にしてみてください!

まとめ 本問の転貸借契約については、すべて基本事項です。基本的なルールを頭に入れていればすべて解ける問題なので、絶対に解けるようにしましょう。
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事