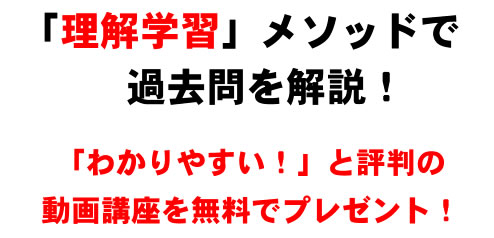Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
- Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
- Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体に被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
- Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
3
解答と解説
【解答】3
選択肢1 Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
【答え】誤り
【解説】
問9-1:相殺を主張する場合、自働債権の期限が満了していることが要件です。.jpg)
本肢の質問内容は「Bは、相殺できる」〇か×か?です。したがって、Bが相殺できれば正しい記述となり、相殺できない場合は誤りの記述となります。 そして、Bから相殺できるかを考えるので、Bの債権である貸金債権が自働債権となります。 貸金債権の弁済期(期限)は12月31日なので、Bは12月31日以降は、相殺可能です。一方、それ以前はBから相殺を主張することはできないので「Bは12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる」という記述は誤りです。相殺ができる要件を押さえて、理解をしておけば、簡単に解けます。 個別指導で詳細解説をします。基本事項なのでしっかり解けるようにしましょう!
選択肢2 Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。
【答え】誤り
【解説】
問9-1:差押えと相殺の対抗関係の図です。.jpg)
本肢では、債権者Cは、11月1日に、Aの代金債権を差押えています。一方、Bは、Aの代金債権の反対債権である「別の債権(金銭債権)」を、11月2日~12月1日の間に取得しています。この場合、Bが反対債権(別の債権)を取得した時期とCが差押えた時期の早い方が対抗できます(勝ちます)。 したがって、Cの差押時期の方が早いので、CがBに対抗できるので、Bは相殺できません。よって、誤りです。
選択肢3 Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体に被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。
【答え】正しい
【解説】
問9-2:人の生命又は身体の侵害に関する不法行為による損害賠償請求権は受働債権として相殺できないことを示した図.jpg)
不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできます。言い換えると、被害者Bから相殺することは可能です。つまり、Bから相殺することは可能なので本肢は正しいです。
<対比ポイント>
不法行為に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を受働債権として相殺することはできません。本肢は、理由が分かれば当然のルールと納得できます。そのため、個別指導では、理由付け勉強法を用いて解説します。理解ができれば、覚える内容でもない位簡単です。
選択肢4 Aは、令和6年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。 BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。
【答え】誤り
【解説】
問9-3:時効完成前に反対債権を取得していないと、時効消滅した債権と相殺を主張することはできない。.jpg)
本肢の状況では、10月1日に、売買契約をしているので、Aは10月1日に代金債権を取得しています。 そして、Bは、貸金債権を持っていたが、9月30日に時効期間が満了して消滅しています。 時効期間が満了した時に(9月30日時点で)、売主Aは、代金債権を取得していません。そのため、買主Bは、時効消滅した貸金債権を自働債権として相殺を主張することができせん。よって、本肢は誤りです。 本肢は、理解すべき内容があるので、個別指導では、理解学習勉強法を使って解説します!無料講座でも理解学習勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!

まとめ この問題を丸暗記勉強法を使っている方は、本試験でひっかけ問題が出題されたときに失点してしまいます。これが合否の分かれ目になります。 勉強した分だけ実力を上げるためにも、しっかり理解学習勉強法を実践していきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
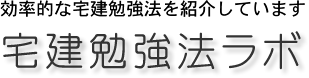
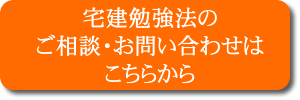
問9-1:相殺を主張する場合、自働債権の期限が満了していることが要件です。.jpg)
問9-1:差押えと相殺の対抗関係の図です。.jpg)
問9-2:人の生命又は身体の侵害に関する不法行為による損害賠償請求権は受働債権として相殺できないことを示した図.jpg)
問9-3:時効完成前に反対債権を取得していないと、時効消滅した債権と相殺を主張することはできない。.jpg)