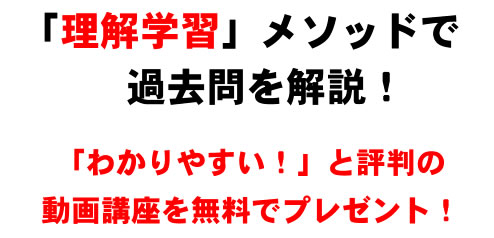国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
4
解答と解説
【解答】4
選択肢1 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
【答え】誤り
【解説】
国土利用計画法の事後届出が必要な場合、事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に行う必要があります。 本肢は「契約締結日の翌日」「3週間以内」の2つが誤りです。
選択肢2 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
【答え】誤り
【解説】
事後届出において、知事が助言・勧告できる内容は、土地の利用目的についてのみです(国土利用計画法27条の2)。本肢のように、「土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額」について助言することはできません。 よって、誤りです。本肢は、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!
選択肢3 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
【答え】誤り
【解説】
事後届出を怠った場合、勧告を受けることなく、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(罰則)に処せられます。本肢は、「都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。」が誤りです。本肢も、関連ポイントがあるので、個別指導では、関連ポイント勉強法を使って解説します!
選択肢4 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
【答え】正しい
【解説】
問22-4:国等が取引相手の場合、事後届出の対象にはなりません。.jpg)
本肢は、A社が、B市に対して10,000㎡の土地を売却し、A社が、C社に対して10,000㎡の土地を売却しています。そして、この合計20,000㎡の土地は 都市計画区域外(準都市計画区域も含む)の土地なので、原則、10,000㎡以上の土地を取得する場合、権利取得者(買主)は、事後届出が必要です。 ただし、国・地方公共団体等との契約については、事後届出に必要な面積に含まず、国・地方公共団体等は自ら買主であったとしても事後届出は不要です。したがって、「A →B市(10,000㎡)」については考えず、「A →C(10,000㎡)」だけ考えればよいです。 よって、本肢の「B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある」という記述は正しいです。本肢は、理解すべき内容があるので、個別指導では、理解学習勉強法を使って解説します!無料講座でも理解学習勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!

まとめ 国土利用計画法における届出制については、理解学習勉強法を使えば、ヒッカケ問題にも引っかからずに済みます。理解すべき部分は理解をして、他の受験生よりも一歩前に出ましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
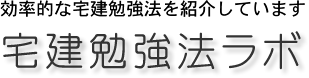
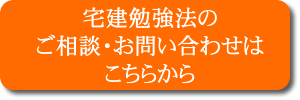
問22-4:国等が取引相手の場合、事後届出の対象にはなりません。.jpg)