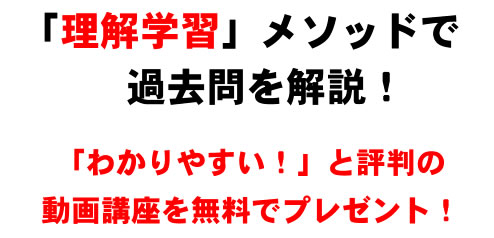不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
- 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
- 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
- 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
♪下記より解答を選んで下さい
 正解!
正解!
1
解答と解説
【解答】1
選択肢1 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
【答え】正しい
【解説】
区分建物(マンション等)が建っている土地が、借地であった場合、この建物を敷地権付き区分建物と呼びます。この場合、「表題部所有者から所有権を取得した者」は、建物自体の所有権保存登記の申請をすることができ、この場合、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。よって、本肢は正しいです。少しわかりづらいかもしれないので、個別指導では、具体例を出して解説します!無料講座でも具体例勉強法の一部を解説しているので参考にしてみてください!
選択肢2 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。
【答え】誤り
【解説】
所有権に関する仮登記に基づく本登記の申請は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、その第三者の承諾が必要です。よって、本肢は誤りです。一方、所有権以外に関するもの(例えば、抵当権)に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、第三者がいても、第三者の承諾は不要です。
選択肢3 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
【答え】誤り
【解説】
問14-3:移転登記請求権の債権者代位を表した図です。.jpg)
本肢の状況を具体例で表すと、上図です。債権者Aとなっていますが、これは「所有権移転登記請求権の債権者」ということです。移転登記をする義務を負っているのがBです。そして、所有権の登記名義人がCにあるので、債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請しています。つまり、所有権が「C→B→A」という風に移転させようと登記申請したことを意味します。そして、Aが債権者代位権の行使により、Cに対して、Bヘの所有権移転登記を求めた場合、登記識別情報はBに通知されます。Aに対して、当該登記に係る登記識別情報が通知されるわけではないので、誤りです。
選択肢4 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
【答え】誤り
【解説】
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、被相続人の所有する建物を相続できなかったとしても、居住する権利を与えて、配偶者の生活を保護するための権利です。そして、建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負うと規定されています。したがって、配偶者居住権は登記可能な権利なので誤りです。

まとめ 不動産登記法は、難しい内容です。本試験で見たことがない問題が出たときは飛ばしてもよいですが、過去問として勉強している場合は、きちんと理解して暗記していく必要があります。すべての選択肢を解けるように理解しておきましょう!
同カテゴリーの前後の記事
前後の記事
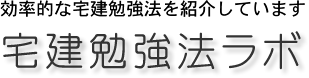
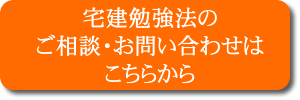
問14-3:移転登記請求権の債権者代位を表した図です。.jpg)